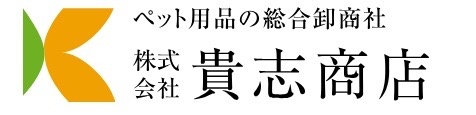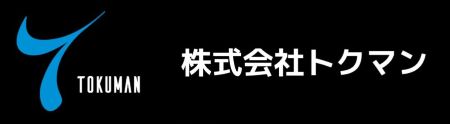【津波警報】その時 ある飼い主の体験談から学ぶペット防災の現実

はじめに:2025年7月30日、突然の警報
2025年7月30日、カムチャッカ半島で発生した大規模な地震の影響で、日本の太平洋沿岸に津波警報・注意報が発表されました。テレビやスマートフォンからは緊迫した情報が流れ、沿岸部の住民は固唾を飲んで状況を見守りました。幸い大きな被害には至りませんでしたが、多くの人が災害の現実を突きつけられ、「もし本当に津波が来たら…」と背筋を凍らせた一日でした。
このような警報は、決して他人事ではありません。
今回、この出来事とは別の機会に、実際に津波警報が発令された北海道で、愛する猫たちと共に避難を試みた一人の飼い主様から、その時の体験談が寄せられました。
日常が非日常へと姿を変える瞬間、ペットと暮らす私たちは何を思い、どう行動するのでしょうか。この貴重な声に耳を傾け、私たちの「ペット防災」について、今一度深く考えていきましょう。
「今すぐ逃げて!」鳴り響く警報と、一人の飼い主のパニック
その日の朝、私はいつものようにテレビを見ていました。「津波があったらしい」というニュース。最初はどこか他人事のように感じ、漁師である夫に電話で知らせた程度でした。
しかし、事態は急速に変化します。
「注意報」が「警報」に変わり、テレビの地図が赤く染まっていく。アナウンサーの「今すぐ逃げて下さい!」という絶叫に近い声。そして、手元のスマートフォンやタブレットが一斉に鳴り出し、けたたましい音で避難を促します。
一気に現実を突きつけられ、パニックに陥りました。でも「猫たちがいる」。その一心で、私は動きました。
万が一の津波に備え、避難ルートは日頃から頭の中でシミュレーションしていました。しかし、実際にその時を迎えると、体は思うように動きません。動悸が激しくなり、手が震えるのを止められませんでした。
急いで2匹の猫をそれぞれのキャリーケースに入れ、車に乗せる。この一連の動作だけでも、平時とは全く違うプレッシャーがかかります。
考え抜いた避難ルート、しかし…
私の住む場所は、決して便利とは言えない辺鄙な場所です。普段は静かな環境が魅力ですが、災害時にはそれが仇となります。近所には人の気配がなく、助けを求めることもできません。夫に何度も電話をかけましたが、全く繋がりませんでした。
「この高台なら大丈夫なのか?」「いや、もっと高い場所へ避難すべきか?」
様々な考えが頭をよぎる中、さらに私を悩ませたのは、家にいる一匹の猫のことでした。その子はやっと我が家に来たばかりで、まだ人慣れしていません。捕まえてキャリーに入れることすら難しい状況だったのです。
避難ルートとして考えていた山道も、途中で行き止まりになります。その先は、キャリーを抱えて歩いて登るしかありません。しかも、その山は熊が出没する可能性もある場所。
「最善の策は、一体何…?」
パニックと焦りの中で、正しい判断を下すことがいかに難しいかを痛感しました。
取り残された猫と、情報のない中での孤独な判断
とりあえず、できる限りのことをしよう。私は猫2匹を乗せた車を、少しでも標高の高い場所へ移動させました。そして、家に残した1匹の猫のために、一度家へと戻ります。
相変わらず、近所には誰もおらず、隣人の車もありません。テレビとスマホは、ただひたすらに警報を鳴らし続け、「避難」を繰り返すばかり。言いようのない不安と孤独感に襲われました。
「海の様子が見える限りは、ここで待機しよう」。そう決めて、ベランダから静かに海を見つめていました。
すると、一台の知らない車が坂を上ってくるのが見えました。同じように避難してきた人でした。「ここは高台だから大丈夫なはずですよ」。その一言に、私はどれだけ救われたか分かりません。ほんの少しだけ、張り詰めていた気持ちが和らぎました。
避難所でペットはどうしているのだろう?
テレビ画面には、避難所に身を寄せた人々の様子が映し出されていました。しかし、そこにペットの姿は見当たりません。
「ペットを飼っている人たちは、みんなどうしているんだろう?」 「あの子たちは、ちゃんと一緒に避難できただろうか?」
自治体ごとにバラバラな対応ではなく、国として統一された、ペットと人間が当たり前に一緒に避難できる防災システムがあれば、どれだけ心強いだろう。心の底からそう思いました。
しばた みき
体験から見えた「ペット同伴避難」のリアルな課題
今回の貴重な体験談は、私たちが日頃から備えるべき「ペット防災」の課題を浮き彫りにしています。
課題1:パニック下での冷静な判断の難しさ 警報音や緊迫した報道は、私たちから冷静さを奪います。事前に避難計画を立てていても、いざとなると体が震え、最善の判断ができない可能性があります。
課題2:避難ルートの脆弱性 「この道なら大丈夫」と思っていても、土砂崩れや渋滞で通れなくなるかもしれません。また、徒歩での避難になった場合、ペット(特に猫や小動物)を連れて長距離を移動するのは極めて困難です。
課題3:複数ペット・在宅ペットへの対応 多頭飼育の場合、全てのペットを一度に避難させるのは非常に大変です。また、人慣れしていない、あるいはケージを嫌がるペットがいる場合、避難自体をためらってしまう危険性があります。
課題4:情報不足と精神的な孤立 災害時、頼れる情報が限られる中で、ペットに関する公的な情報は後回しにされがちです。周囲に相談できる人がいない状況は、飼い主を精神的に追い詰めます。
「もしも」を「いつも」の備えに。今すぐできるペット防災
この体験談を「大変だったね」で終わらせず、私たち自身の備えに繋げることが何よりも重要です。NPO法人ペット防災ネットワークでは、具体的なアクションプランとして、以下の3つのステップを推奨しています。
ステップ1:ハザードマップで災害リスクを「知る」 まず、お住まいの地域のハザードマップを確認し、自宅や周辺にどのような災害リスク(津波、洪水、土砂災害など)があるのかを正確に把握しましょう。その上で、安全な避難場所と、そこへ至る複数の避難ルートを検討しておくことが、全ての備えの第一歩です。
ステップ2:避難訓練で現実に「試す」 寄稿者の方が「実際に避難訓練をしておけば…」と感じたように、シミュレーションは非常に重要です。 「天気の良い休日に、実際にペットをキャリーに入れ、避難場所まで歩いてみる」 これだけでも、多くの気づきがあるはずです。「キャリーが重すぎる」「猫が鳴き続けてしまう」「この道は夜だと暗くて危険だ」など、リアルな課題が見えてきます。課題が見えれば、対策も具体的に考えられます。
ステップ3:地域との繋がりで孤立せず「備える」 今回の体験談でも、避難してきた人との一言の会話が大きな安心に繋がりました。日頃からご近所の方と「ペットを飼っているんですよ」とコミュニケーションを取っておくだけで、いざという時に「あそこのお宅は猫ちゃんがいたな」と気にかけてもらえるかもしれません。信頼できる友人に、万が一の際のペットのお世話を頼んでおく「預け先相互扶助」も有効な備えです。
まとめ:統一された支援システムと、あなたの一歩
「自治体ごとにバラバラな対応ではなく、きちんとしたペットと人間の防災システムがあったらいいのに」。
これは、被災したすべての飼い主が抱く、切実な願いです。環境省のガイドラインではペットとの「同行避難」が原則とされていますが、その運用は自治体に委ねられているのが現状です。
私たちNPO法人ペット防災ネットワークは、この声を行政に届け、人とペットが当たり前に「同行避難」できる社会の実現を目指して活動しています。
災害は、いつ、どこで起こるか分かりません。このリアルな体験談を胸に刻み、あなたと、あなたの愛する家族であるペットのために、今日からできる「ペット防災」を始めてみませんか。私たちも、セミナーなどを通じてそのお手伝いを続けていきます。