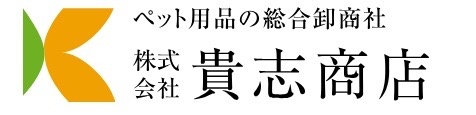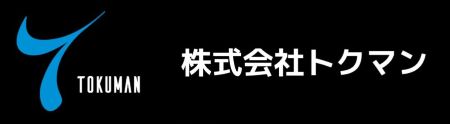災害時の「住まいの壁」- みなし仮設住宅におけるペット飼育の課題と、私たちが目指す未来

はじめに:当たり前になった「同行避難」、しかしその先に潜む障壁
熊本地震から10年近くが経過し、社会の防災意識は大きく変化しました。かつては困難とされたペットとの「同行避難」は、今や環境省のガイドラインにも明記され、多くの自治体で受け入れ体制の整備が進むなど、社会の共通認識となりつつあります。これは、ペット防災に関わる全ての人が長年声を上げ続けた結果であり、大きな前進であることは間違いありません。
しかし、「同行避難」はゴールではありません。むしろ、被災したペットと飼い主の長く困難な道のりの、ほんの始まりに過ぎないのです。避難所で当面の安全を確保したのち、彼らが直面するのは「生活再建」という、より現実的で切実な課題です。特に、その基盤となる「住まい」の確保において、見過ごされてきた巨大な障壁が存在します。
それが、民間の賃貸住宅を自治体が借り上げて提供する「みなし仮設住宅」制度における、深刻なペット可物件の不足問題です。
ある調査では、日本のペット飼育世帯の割合が約28.6%にのぼる一方、賃貸市場に出回るペット可物件の割合はわずか19.3%に過ぎないと報告されています。この約10%のギャップは、平時であれば「根気よく探せば見つかる」程度の不便さかもしれません。しかし、全てを失い、心身ともに疲弊した被災者にとっては、生活再建そのものを諦めさせるほどの絶望的な壁となって立ちはだかるのです。
今回は、災害時のペット支援におけるこの「住まいの断絶」に深く切り込み、その構造的な課題を分析するとともに、私たちNPO法人ペット防災ネットワークが提唱する新たな解決策について、具体的な提言を行います。
見過ごされてきた「住まいの断絶」 – なぜペットと入れる家が見つからないのか
「みなし仮設住宅」制度は、プレハブ等の応急仮設住宅が建設されるまでの間、あるいはそれに代わる選択肢として、被災者が地域の民間賃貸住宅に入居できるよう、国と自治体が家賃を負担する仕組みです。住み慣れた地域を離れることなく、プライバシーが確保された環境でいち早く日常を取り戻せるため、被災者の心身の回復に大きく貢献する優れた制度と言えます。
しかし、この制度は、あくまで「既存の民間賃貸市場に存在する物件」を借り上げるという前提に成り立っています。ここに、ペットを飼う被災者にとっての大きな落とし穴があります。
前述の通り、日本の賃貸市場は、ペット飼育者に対して決して開かれているとは言えません。需要に対して供給が圧倒的に追いついていないのが現状です。この構造的な問題は、大規模災害が発生するたびに、深刻な形でその姿を現してきました。
2016年の熊本地震では、私たちも現地で支援活動を行う中で、この現実に直面しました。ペットとの同行避難を無事に終えた方々が、次に「みなし仮設住宅」を探そうとしても、そもそも選択肢となるペット可物件が地域にほとんど存在しないのです。仮に見つかったとしても、家賃が自治体の定める上限額を超えていたり、大型犬は不可であったり、場所が遠かったりと、厳しい条件がさらに追い打ちをかけます。
その結果、多くの被災者が、 「ペットと避難したのに、一緒に暮らせる家がない」 「この子を手放さなければ、私たちは家に住めないのか」 といった、あまりにも理不尽で残酷な選択を迫られました。国や自治体が「ペットとの同行避難」を推奨し、その命を守るよう呼びかけながら、その先の生活を支えるべき住宅制度が、事実上、彼らを家族から引き離す装置として機能してしまっている。この矛盾こそが、日本の災害時ペット支援における「住まいの断絶」の正体です。この問題は、東日本大震災でも、近年の能登半島地震でも形を変えて繰り返されており、日本の災害対応における普遍的かつ喫緊の課題なのです。
供給が増えない根本原因 – 貸主の不安と、問われる飼い主の「覚悟」
では、なぜこれほど需要があるにも関わらず、ペット可の賃貸物件は増えないのでしょうか。その根源には、物件を提供する貸主(オーナー)側の根深い不安があります。
ある調査では、貸主がペットを不可とする理由として、74.2%が「物件の破損や汚れ」を挙げています。爪による傷、臭いの染みつきなどは、退去時の原状回復費用を押し上げ、通常の1.5倍から2倍、場合によっては100万円を超える高額な修繕費が発生したという事例も報告されています。さらに、鳴き声や足音をめぐる「騒音トラブル」は、他の入居者からのクレームに直結し、その対応は貸主や管理会社にとって大きな精神的負担となります。
これらのリスクは、金銭的な補填(家賃の割増や敷金の追加)だけでは完全には解消できません。だからこそ多くの貸主が、安定した経営のために「ペット不可」という選択をせざるを得ないのです。
この状況を打開し、貸主の不安を和らげ、市場全体の信頼を醸成するために不可欠なのが、私たち飼い主一人ひとりの責任ある行動です。これは単なる「マナー」の問題ではなく、社会の一員としての「覚悟」と言い換えてもいいかもしれません。
日頃からの徹底したしつけ: 無駄吠えをコントロールし、基本的な指示に従えるようにする。ケージやキャリーバッグを「安心できる自分の部屋」として認識させるハウストレーニングは、避難生活だけでなく、共同住宅での暮らしにおいても極めて重要です。
適切な健康・衛生管理: 定期的なワクチン接種やノミ・ダニ駆除はもちろん、ブラッシングやシャンプーで体を清潔に保ち、臭いを抑える努力をする。排泄物の適切な処理は言うまでもありません。
周囲への積極的なコミュニケーション: エレベーターで乗り合わせる際に一声かける、廊下ですれ違う際に挨拶するなど、日頃から近隣住民と良好な関係を築く努力が、いざという時の相互理解に繋がります。
こうした地道な努力の積み重ねが、「ペットを飼っている入居者は、責任感があり信頼できる」という社会的な評価を創り上げます。それが、貸主の不安を払拭し、「あなたになら安心して貸せる」という物件を一つでも増やす力になるのです。平時の私たちの行動が、災害時に自分たちを救うセーフティネットを編むことに他なりません。
信頼のコミュニティを築く – 「飼い主の会」という新たな解決策
飼い主個人の努力(自助)を社会全体で推進していくと同時に、私たちはもう一歩踏み込んだ仕組みが必要だと考えています。それが、ペット可の共同住宅(賃貸マンションや仮設住宅)において、入居者自身が主体となる「飼い主の会」を設立・運営するというアプローチです。
トラブルの多くは、ルールが曖昧であること、そして住民間のコミュニケーションが不足していることに起因します。ならば、入居者自身がコミュニティを形成し、自分たちの手で住みやすい環境を創り上げていく「共助」の仕組みを導入するのです。
「飼い主の会」が担う役割は多岐にわたります。
1. 自主的なルール作りと合意形成: 「夜10時以降は静かにさせる」「共用廊下では必ずリードを短く持つ」など、法律や賃貸契約書には書かれていない、その住宅の実情に即した具体的な飼育ルールを入居者同士の話し合いで決め、全員で遵守することを約束します。
2. トラブルの自主解決機能: 万が一、騒音などの問題が発生した場合、まずは会の中で当事者同士が話し合い、解決を目指します。いきなり管理会社や行政にクレームを入れるのではなく、コミュニティ内部で解決する努力をすることで、外部の負担を軽減し、住民間の関係悪化を防ぎます。
3. 情報交換と相互扶助(共助)の拠点: 近所の評判の良い動物病院の情報を交換したり、しつけの悩みを相談しあったり。平時から顔の見える関係を築くことで、災害時には「停電で不安がるペットのために集まる」「フードが足りない世帯に分け与える」「飼い主が負傷した際に、一時的にペットを預かる」といった、命を繋ぐ共助ネットワークが自然に機能するようになります。
このような責任あるコミュニティの存在は、貸主や、ペットを飼っていない他の住民にとって、何よりの安心材料となります。「あのマンションの飼い主さんたちは、自分たちでしっかりルールを決めて運営している」という信頼が生まれれば、それは物件全体の資産価値向上にも繋がるでしょう。
私たちにできること – 「飼い主の会」設立・運営ノウハウの提供
しかし、「飼い主の会」という理念は素晴らしくても、実際にゼロから立ち上げ、円滑に運営していくことは簡単ではありません。「何から始めればいいのか」「住民同士で意見が対立したらどうするのか」といった不安を感じる方も多いでしょう。
そこで、私たちNPO法人ペット防災ネットワークが、その設立と運営を全面的にサポートします。
私たちは、熊本地震をはじめとする数々の災害現場での支援活動や、全国の自治体・専門家との連携を通じて、ペットと共生するコミュニティ運営に関する豊富な知見とノウハウを蓄積してきました。その専門性を活かし、以下のような具体的な支援を提供することが可能です。
規約・ルール案のテンプレート提供: 様々な住宅形態やコミュニティの規模に応じた、規約やルールのひな形をご提供し、スムーズな立ち上げを支援します。
合意形成のファシリテーション: 住民間の話し合いが円滑に進むよう、私たちが第三者の専門家として議論の場に立ち会い、意見の整理や論点の明確化をお手伝いします。
専門家ネットワークの活用: 私たちのネットワークを通じて、獣医師による健康相談会や、ドッグトレーナーによるしつけ教室などを「飼い主の会」のイベントとして開催する企画・仲介を行います。
全国の成功事例の共有とコンサルティング: 他の地域で成功している「飼い主の会」の活動事例をご紹介し、それぞれのコミュニティに合った運営方法を一緒に考えます。
この支援を通じて、実効性のある「飼い主の会」を全国に増やしていくこと。それが飼い主コミュニティ(共助)を強化し、ひいては貸主の信頼を得てペット可物件を増やすという、市場全体の変革に繋がっていくと信じています。
最終目標:官民連携による「命を繋ぐプラットフォーム」の構築
飼い主の「自助」と、飼い主の会の「共助」。この二つの歯車を力強く回していくと同時に、私たちは最終的な目標として、官民が連携する全国規模の「プラットフォーム」の構築を掲げています。
このプラットフォームの中核となるのが、全国のペット可住宅情報を集約したデータベースです。その目的は、災害時と平時の両方において、ペットと暮らす家を必要としている飼い主と、受け入れ可能な住宅とを、自治体と連携しながらシームレスに繋ぐことです。
災害発生時、私たちはこのデータベースを被災自治体と瞬時に共有します。これにより、行政は混乱の中でも「どのエリアに、どのような条件のペット可住宅が存在するのか」を即座に把握でき、被災者への迅速な情報提供や「みなし仮設住宅」としての斡旋が可能になります。これは単なる物件リストではなく、有事に飼い主とペットの命と暮らしを守るための、不可欠な情報インフラです。
そして、このプラットフォームは災害時だけに機能するものではありません。平時においても、これからペットと暮らしたい、あるいはより良い環境へ住み替えたいと願う飼い主にとって、信頼できる情報源となります。
さらに重要なのは、このプラットフォームが単に物件を仲介するだけでなく、コミュニティを育て、「適正飼育」の文化を社会に根付かせる機能を持つことです。
例えば、データベースに登録された物件情報の中に、「『飼い主の会』が設立され、活発に運営されています」「定期的に専門家を招いたしつけ教室が開催されています」といった付加情報を掲載します。これにより、家を探す飼い主は、ハード面だけでなく、コミュニティというソフト面も重視して住まいを選ぶようになります。
こうした仕組みは、物件オーナーにとっても、「飼い主の会」の設立を支援することが物件の付加価値を高め、意識の高い入居者を惹きつける強力なアピールになるというインセンティブを生み出します。つまり、このプラットフォームは、適正飼育に積極的に取り組むコミュニティが評価され、選ばれる市場を創出するのです。
このように、飼い主、貸主、行政のそれぞれにメリットがある仕組みをデザインすることで、平時にはペットと共生しやすい社会の基盤を育み、災害時には被災した飼い主と受け入れ可能な住宅を迅速かつ的確に繋ぐ、強力なセーフティネットとして機能させることができるのです。
まとめ:断絶を繋ぎ、誰一人、一頭も取り残さない社会へ
災害時のペット支援は、避難所という「点」の支援から、生活再建という「線」の支援へ、そして社会システム全体を変革する「面」の支援へと、そのステージを大きく進化させるべき時期に来ています。
「みなし仮設住宅」をめぐる根深い課題は、飼い主、不動産業界、行政、そして私たちNPOがそれぞれの専門性とリソースを持ち寄り、垣根を越えて連携しなければ、決して乗り越えることはできません。
自助: 飼い主一人ひとりが、社会の一員としての責任と覚悟を持つこと。
共助: 飼い主同士が繋がり、信頼と安心のコミュニティを育むこと。
公助: 行政が、現実の課題に即した実効性のある制度を設計し、民間の努力を後押しすること。
この三つが有機的に連携して初めて、ペットと暮らすことがリスクではなく、社会を豊かにする価値であると誰もが認められる未来が拓けます。
私たちNPO法人ペット防災ネットワークは、この断絶された関係を繋ぎ、未来へのビジョンを共有するための触媒(ハブ)としての役割を全力で担っていく所存です。この活動は、私たちだけの力では決して成し遂げられません。
この記事を読んでくださっている自治体、事業者、そして市民の皆様。どうかこの「住まいの断絶」という課題に目を向け、関心をお寄せください。そして、私たちの活動のサポーターとなって、誰一人、そして一頭も取り残さない、真に強靭で心豊かな社会を、どうか一緒に創り上げてください。