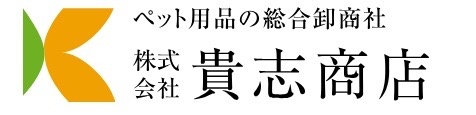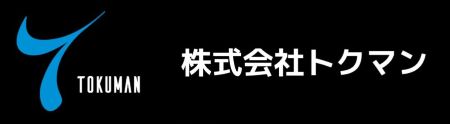「私がそれになる」と決めた日から。地域でペット防災の輪を広げる。

はじめに:すべての始まりは、雑談の中の一言だった
「災害が起きた時、避難所にペットを連れてきたら、きっと現場は混乱する。飼い主さんも本当に困るはず。その場をうまく整理して運営する人が必要だよね。私たちドッグライフカウンセラーが、その役割を担えたらいいのに」
今、私のペット防災活動の原点となっているのは、2013年にドッグライフカウンセラーの資格を取得した後、仲間たちと交わした何気ない雑談の中のこの一言でした。この言葉を聞いた瞬間、まるで啓示を受けたかのように「私が、それになる」と、心の奥深くで固い決意が生まれたのを、今でも鮮明に覚えています。
しかし、その決意はあまりに漠然としていました。「その役割」にたどり着くための道筋は全く見えず、まるで雲を掴むような感覚でした。それでも、心の内に灯った小さな火を消したくない一心で、私はペット防災の世界へ一歩ずつ足を踏み入れていくことになります。これが、地域社会、そして行政を巻き込みながら、仲間と共にペット防災の輪を広げていく活動の、まさに始まりだったのです。
第1章:模索の始まりと地域との接点
決意を固めたものの、具体的に何をすれば良いのか分かりませんでした。まずは知識を得ようと、ペット防災に関連するセミナーへ積極的に参加し、専門の資格を取得するための講座も受講しました。幸い、ドッグライフカウンセラーの仲間内でもペット防災への関心は高く、有志による勉強会で「ペット防災」をテーマに取り上げました。
その勉強会で「まず、それぞれが自分の住む地域のペット防災の取り組みを調べてみよう」という話になりました。早速、私は自宅のある東京都練馬区のホームページを検索しました。すると、「生活衛生課」が「災害時ペット管理ボランティア」を募集しているという情報が目に飛び込んできたのです。
「自分の地域に、こんな制度があったのか!」
正直、驚きました。同時に、自分が探し求めていた役割への扉が、すぐ目の前にあったことに胸が高鳴りました。私は迷わず応募をしました。この「災害時ペット管理ボランティア」こそが、私のその後のペット防災活動の揺るぎない中心軸となっていくのです。
応募後、すぐに区役所で面談が行われ、活動内容について詳しい説明を受けました。練馬区では、区立の小・中学校98ヶ所を、単なる「避難所」ではなく「避難拠点」と名付けているとのこと。これは、災害時における地域の活動拠点となるからだそうです。
そして、ボランティアに求められる役割は、まさに私が雑談の中で聞いた「理想の姿」そのものでした。災害時にペットと共に避難(同行避難)してきた飼い主さんが、避難拠点で適切にペットの飼育・管理ができるよう手助けをし、ペットをめぐるトラブルや混乱を防ぐこと。これこそが、私が「なりたい」と願った役割でした。
「まずは、お住まいの近くの避難拠点を担当していただき、平時から避難拠点の会議や訓練に参加して、運営連絡会の方々に顔を覚えてもらうことから始めてください」
担当者のその言葉に、私は地域に根差した活動の第一歩が始まると、大きな期待を膨らませていました。2017年、正式にボランティアとして登録が完了。しかし、この時、私の前には想像もしていなかった大きな壁が立ちはだかることになるのです。
第2章:見えない壁との闘い – 2年間の停滞
ボランティア登録を終え、担当する避難拠点から連絡が来るのを今か今かと待っていました。しかし、1ヶ月が過ぎ、半年が過ぎ、1年が過ぎても、何の音沙汰もありません。地域の町会にも加入していなかった私には、避難拠点運営連絡会に自らアプローチする術もなく、ただ時間だけが過ぎていきました。
「このままではいけない」
焦りを感じた私は、自分なりにできることを探しました。偶然、別の避難拠点で行われる防災訓練の情報を知り、主催者に許可も得ず、勝手に愛犬を連れて参加してみたこともあります。「ペットとの同行避難は大切なんです!」と、参加者にアピールしてみましたが、単発の活動では大きな変化は望めません。
区役所の担当課である生活衛生課にも、担当避難拠点と繋いでほしいと何度も問い合わせをしました。しかし、返ってくる答えはいつも「管轄の区民防災課には伝えています」というもの。状況は一向に好転しませんでした。
結局、ボランティアに登録してから2年以上もの歳月が流れてしまいました。この時、私が直面していたのは、いわゆる「縦割り行政」の壁でした。ボランティアの登録や管轄は「生活衛生課」、しかし、ボランティアが実際に活動する避難拠点の運営や訓練を管轄しているのは「区民防災課」。二つの課の間で、情報や連携がうまく機能していなかったのです。ペット防災という分野が、まだ行政の中で「どの課が主導すべきか」という点で確立されていなかったのかもしれません。
熱意だけではどうにもならない現実に、無力感を覚える日々。しかし、あの日の決意を諦めることはできませんでした。
第3章:突破口 – 一通のメールが流れを変えた
2019年、しびれを切らした私は、最後の望みをかけて行動に出ます。以前、別の防災訓練に参加した際に名刺交換をしていた区民防災課の職員、K氏に直接メールを送ったのです。
「災害時ペット管理ボランティアに登録している者です。担当避難拠点で活動したいのですが、繋いでいただけないでしょうか」
正直、あまり期待はしていませんでした。しかし、返信は驚くほど早く、そして意外なものでした。
「ぜひ、お話をお聞かせください!お待ちしていました!」
大歓迎とも言えるその内容に、私はすぐさま区民防災課へ向かいました。K氏は非常に熱心な方で、私のこれまでの経緯とペット防災への想いを真摯に受け止めてくれました。そして、あれほど繋がらなかった担当避難拠点との間を、いとも簡単につないでくれたのです。
この出来事は、私に大きな教訓を与えてくれました。縦割り行政という大きな壁も、熱意ある「個人」との出会いによって突破できることがあるのだと。そして、K氏との出会いは、さらに大きな広がりを生んでいくことになります。彼は、他の避難拠点で同じように活動しているペットボランティアを紹介してくれたのです。
それをきっかけに、点と点だったボランティア同士が繋がり始めました。連絡先を交換し、情報共有のためのLINEグループが誕生。一人で抱えていた悩みや情報を共有できる仲間を得たことで、私の活動は停滞期を乗り越え、一気に加速していくことになったのです。
第4章:仲間と共に – 念願のペット同行避難訓練の実現
ボランティア同士がLINEグループで繋がったことで、孤独な活動は終わりを告げました。コロナ禍で一時的に活動が制限されたものの、私たちはオンラインで情報交換を続け、来るべき時に備えていました。
そして2021年、避難拠点での防災訓練が再開されることになりました。私は、この機会に本格的な「ペット同行避難訓練」を実施したいと強く思うようになりました。勇気を出し、区民防災課のK氏に連絡を入れると、返ってきたのは「大賛成です!ぜひやりましょう!」という即答でした。
私の提案に対し、K氏は学校(避難拠点)への協力依頼、事前打ち合わせのセッティングなど、全ての調整を迅速に進めてくれました。幸い、学校側や運営連絡会から反対意見が出ることもなく、ついに担当避難拠点でのペット同行避難訓練の実施が決定しました。
さらに、驚くべきことに、災害時のペットの避難場所として、これまで想定されていた屋外のスペースではなく、校舎内の「図工室」を使用させてもらえることになったのです。これは、ペットと飼い主の安全・安心を確保する上で非常に大きな前進でした。
初めての訓練実施にあたり、私一人では到底手が足りません。LINEグループで仲間に協力を呼びかけると、「手伝うよ!」「一緒にやりたい!」と、数名のボランティアがすぐに名乗りを上げてくれました。
訓練当日、私たちは受付担当、誘導担当、飼育スペース設営担当と役割を分担し、参加してくれた地域の飼い主さんたちを迎えました。受付でのペット情報の確認、ケージやクレートの配置、飼い主さんへの注意事項の説明など、仲間がいたからこそ、スムーズで実践的な訓練を行うことができました。この日の成功体験は、私たちにとって大きな自信となりました。
第5章:活動の組織化と行政の変化
一回の訓練成功に満足することなく、私たちはこの流れをさらに大きなものにしたいと考えました。2022年3月、LINEグループで繋がっているボランティア有志による、初の自主交流会が実現。会議室を借り、2ヶ月に1回のペースで定期的に開催することになりました。
交流会では、それぞれの活動状況や悩みを共有しました。
「ボランティアに登録したものの、何から手をつけていいか分からない」
「どうすれば避難拠点運営連絡会に参加できるのか知りたい」
皆、担当地域で孤軍奮闘し、同じような壁にぶつかっていたことが分かりました。しかし、交流会やLINEグループでの情報共有は、互いを力強く刺激しました。「あの地域ではこんな啓発活動をやっているらしい」「この資料が分かりやすいよ」といった情報が、それぞれの地域での活動に活かされ、練馬区全体のペット防災のレベルを底上げしていく力となっていったのです。
そして2023年の春、私たちの活動がひとつの実を結ぶ、画期的な出来事が起こりました。生活衛生課が制作した「動物避難所開設用キット」が、区内98ヶ所の全ての避難拠点に配備されたのです。これは、災害発生直後に避難所の運営者が最低限の対応を行えるようにするための、いわゆる「スターターキット」の練馬区版でした。
内容は簡易的なものでしたが、これは私たちボランティアが地道に声を上げ、活動を続けてきた成果が行政を動かした証でした。そして何より、これまで連携が課題だった生活衛生課と区民防災課が、協力してこのキットを配備したという事実が、私たちを勇気づけてくれました。
おわりに:私の活動源であり、宝物
行政は人事異動がつきものです。私の担当避難拠点の防災課担当者も、この数年で3人替わりました。しかし、幸いなことに、「防災訓練のメニューにペット関連の内容を取り入れる」という方針は、後任の方々にもしっかりと引き継がれています。ペット同行避難訓練や、ペットの避難に関する講話などを、毎年継続して実施できています。
正直に言えば、今でも避難拠点運営連絡会の中で、ペット防災の担当は私一人です。自分が声を上げなければ、議題に上がることすらないかもしれない、というプレッシャーや心細さを感じることもあります。負担が大きいと感じる瞬間も少なくありません。
それでも私がこの活動を頑張れるのは、間違いなく、同じ練馬区内で切磋琢磨しているボランティア仲間たちの存在があるからです。一人では乗り越えられなかった壁も、仲間がいたから突破できました。一人では見つけられなかった答えも、仲間と知恵を出し合うことで見つかりました。このメンバーとの繋がりこそが、私の活動源であり、かけがえのない宝物です。
この記事を読んでくださっているあなたも、「自分の地域で何かできないか」と考えているかもしれません。その第一歩は、ご自身の自治体のホームページを調べることかもしれませんし、私たちのNPO法人が開催するようなペット防災セミナーに参加して知識を得ることかもしれません。
一個人の小さな決意から始まった活動が、仲間と繋がり、行政を動かし、地域の防災力を高める力になる。私の経験が、これからペット防災活動を始めようとする方々、そして今まさに活動の中で壁に直面している方々にとって、少しでも勇気やヒントとなれば幸いです。
ドッグライフカウンセラー/練馬区災害時ペット管理ボランティア 小川京子
NPO法人ペット防災ネットワークのペット防災セミナーはこちら