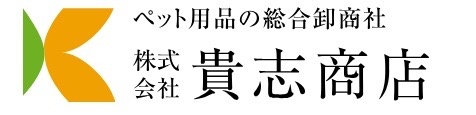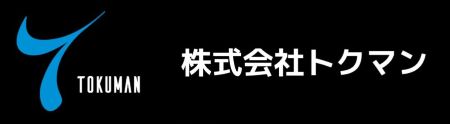ペット防災とは何か?「益城町わんにゃんハウス」”被災者支援”としてのペット防災

はじめに:「動物の救済」だけではない、もう一つの災害ペット支援
「災害時のペット支援」と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのは、被災した動物たちを救うために寝る間も惜しんで現地で活動する動物愛護団体の姿かもしれません。瓦礫の中から救出されるわんちゃんやねこちゃんの映像は、私たちの胸を打ちます。
もちろん、そうした尊い活動も災害支援の重要な一側面です。しかし、2016年の熊本地震で震度7を2度観測し、甚大な被害を受けた熊本県益城町に開設された「益城町わんにゃんハウス」では、それとは全く異なるアプローチで、被災したペットとその飼い主を支える、もう一つの支援の形がありました。
それは、「動物愛護」という枠組み以上に、「被災者支援」という視点に重きを置いたものでした。ペットをただ”保護”の対象として見るのではなく、かけがえのない家族の一員として愛する「飼い主」という被災者に寄り添い、その生活再建を支えること。
この記事では、私たちが運営に深く関わった「益城町わんにゃんハウス」の軌跡を辿りながら、これからのペット防災、ひいては災害支援のあり方について考えていきたいと思います。
「益城町わんにゃんハウス」保護シェルターではない、飼い主とペットのための”家”
開設の経緯:避難所で突きつけられた現実
そもそも「益城町わんにゃんハウス」は、いわゆる被災ペットの保護シェルターではありませんでした。動物愛護団体が主体となって動物を保護・管理し、飼い主が見つかるまでの一時的な避難場所を提供する施設とは、その目的も運営方法も明確に一線を画していました。
このプロジェクトは、地震発災直後の混乱の中から生まれています。多くの飼い主が、大切な家族であるペットと共に避難所へ身を寄せました。しかし、「動物が苦手」「アレルギーがある」といった声や衛生面への懸念から、ペットを避難所内に留めておくことは次第に困難になり、屋外の車や軒下などに繋がざるを得ない状況に直面したのです。
余震が続く不安の中、慣れない環境で心身ともに疲弊していく飼い主とペットたち。この状況を何とかしなければならない。私たちも益城町総合体育館で飼い主と共に室内に避難していたペット支援を行う中で、益城町からやがてペットは屋外に出されるという情報を知らされました。、体育館にいた16世帯、犬16頭、猫4頭。そしてテントにいた飼い主とペットたち。彼らの行き場が、またしても失われようとしていました。
急遽、総合運動体育館の施設管理者であるYMCAと協議を重ねました。そして、敷地内にコンテナハウスを複数設置し、飼い主とペットが共に過ごせる「益城町わんにゃんハウス」を開設するに至ったのです。
運営の根幹は「飼い主の主体性」
当初、運営資金は寄付を募って賄う予定でした。しかし、私たちの活動方針が、やがて大きな支援の輪を引き寄せます。
私たちは発災直後から、避難所にいるペットの飼い主さんたちに「飼い主の会」の立ち上げてもらっていました。それは、「被災者だから」と受け身になるのではなく、一人の飼い主として、自らのペットの命と生活に責任を持つという自覚を促すためです。この飼い主自身が主体的に関わる運営方針、そして益城町、施設管理者との密な連携体制が評価され、環境省が「これは被災者支援の新しいモデルケースになり得る」として、運営を支援してくれるという幸運な申し出をいただいたのです。
これにより、わんにゃんハウスは、行政・施設管理者・飼い主・そして私たち支援団体が一体となって運営する、前例のない拠点となりました。
厳しいけれど、当たり前の「入居条件」
わんにゃんハウスの入居条件。それは、単にペットを預かるのではなく、飼い主とペットの「暮らし」を支えるという理念に基づいています。
飼い主自身がペットのお世話(清掃、給餌、散歩など)を毎日行うこと
わんにゃんハウスの自治組織である「わんにゃんハウス飼い主の会」に参加すること
月に一度、入居者全員で行う施設の大掃除に参加すること
一見すると、被災した方々に対して厳しい条件に思えるかもしれません。しかし、これはペットと暮らす上で「当たり前」のことです。災害時だからといって、その責任が免除されるわけではありません。むしろ、困難な状況だからこそ、飼い主としての責任を果たし続けることが、ペットの心身の健康、そして飼い主自身の尊厳を守ることに繋がるのです。
私たちスタッフの主な仕事は、ケージの管理や直接的なお世話ではなく、飼い主さんたちへのサポートと、適正な飼育に関するアドバイスでした。主役は、あくまで飼い主自身。この徹底した方針が、わんにゃんハウスを単なる「避難場所」ではない、特別な「コミュニティ」へと昇華させていくことになります。
いつもの「お世話」が取り戻させた”日常”〜非日常の避難生活で心を保つということ
戸惑いから生まれた、飼い主としての自信
突然の災害で家を失い、先の見えない避難生活。それまでペットをケージに入れた経験すらなかった飼い主さんたちにとって、わんにゃんハウスでの生活は戸惑いの連続でした。開設当初は、「狭いケージに入れるなんてかわいそう」「ここで本当にやっていけるだろうか」といった不安の声を口にする方も少なくありませんでした。
しかし、その不安は、日々の暮らしの中で少しずつ解消されていきます。スタッフや全国から集まったボランティアの方々が、ケージ内の環境づくりの工夫を伝え、わんちゃんのストレスを少しでも和らげる散歩の仕方をアドバイスする。そして何より、飼い主さん自身が毎日欠かさずケージを掃除し、ご飯を与え、散歩に連れて行く。その繰り返しの中で、「自分はこの子の命を守っている」という飼い主としての自信と責任感が、不安を乗り越える力に変わっていきました。
ペットのお世話が繋ぎ止めた「普段の暮らし」
被災生活は、すべてが「非日常」です。寝る場所も、食べるものも、周囲の環境も、昨日までとは全く違う。人は、こうした非日常が続くと、知らず知らずのうちに精神のバランスを崩しやすくなります。
そんな中で、愛するわんちゃん、ねこちゃんのお世話をするという行為は、被災する以前と変わらない「日常」の感覚を保つための、非常に重要な”錨(いかり)”となりました。「朝になったら、この子のために起きなくては」「夕方には散歩に連れて行かなくては」。その決まったリズムが、先の見えない不安な日々の中に、確かな生活の軸を与えてくれたのです。
ペットに触れ、世話をすることで得られる癒やし(アニマルセラピー効果)はもちろんですが、それ以上に、「誰かのために責任ある行動を続ける」ということが、被災された方々の心を強く保つ一助となっていたことは、わんにゃんハウスがもたらした大きな発見の一つでした。
”共助”が育んだ温かいコミュニティ〜「飼い主の会」が果たした大きな役割
わんにゃんハウスのもう一つの大きな特徴は、飼い主さん同士の「共助」の姿がごく自然に生まれていたことです。
「お互い様」が生んだ助け合いの輪
被災者だからといって、みなさん避難所でじっとしている訳ではありません。自宅の瓦礫の片付け、行政での複雑な手続き、そして仕事を再開する方もいます。朝早くから出かけなければならず、わんちゃんの朝の散歩に連れて行けない日もあれば、疲れて帰ってきてケージの清掃が間に合わない、そんな日もありました。
しかし、そんな時は決まって誰かが声をかけます。「うちの子の散歩に行くから、一緒に行きましょうか?」「隣だから、ついでに掃除しておきますよ」。隣のケージの飼い主さんが、ごく自然に手を差し伸べるのです。そこには「被災者同士、お互い様」という温かい空気が流れていました。同じ境遇で、同じようにペットを愛する者同士だからこそ生まれる、強い絆がそこにはありました。
主体的な運営参加が「支援される側」から「支え手」への意識を変えた
入居条件であった「わんにゃんハウス飼い主の会」は、単なる名ばかりの組織ではありませんでした。月に一度の定例会では、飼い主さんたちがみんなで手分けをして効率よく、しかも丁寧に清掃を行ってくれたので清掃もあっという間に終わります。また、何度も続く余震、大きな余震があった際はそれが夜中でも飼い主の会の誰かが、必ず、ペットたちの安全確認を行ってくれていました。
自分たちの場所は自分たちで管理する。このプロセスは、飼い主さんたちの意識を「支援される側」から、ハウスを共に運営する「支え手」へと変えていきました。この当事者意識こそが、わんにゃんハウスを円滑に、そして温かく運営していくための原動力となったのです。
飼い主、ボランティア、行政、そして私たち運営者が一体となってハウスを運営する、まさに「コミュニティ」そのものでした。
心のケアとしての支援〜全国から届いた多様な温もり〜
動物愛護の枠を超えたボランティアの力
わんにゃんハウスには、北は北海道から南は沖縄まで、本当に多くの方々がボランティアとして駆けつけてくれました。意外なことに、その中にいわゆる動物愛護団体の方々の姿はほとんどありませんでした。
集まってくれたのは、夏休みを利用した学生さん、フィギュアスケートの羽生結弦選手のファンクラブの方々、被災したわんちゃんたちを綺麗にしてあげたいと申し出てくれたトリマーさん、そして、遠く北海道からやってきた作家さんなど、これまで「動物愛護」という言葉とは直接結びつかなかったような、多様な背景を持つ人々でした。
もちろん、地元熊本の獣医師会も、専門的な見地から健康相談やアドバイスなど、力強い支援を提供してくださいました。
忘れられない、手作りのキーホルダー
数々の温かい支援の中でも、特に私たちの心に深く刻まれているエピソードがあります。北海道からボランティアに来てくださった作家さんが、わんにゃんハウスにいた全てのわんちゃんとねこちゃんの写真を撮り、北海道に戻った後、その一体一体の特徴を捉えた木製のキーホルダーを手作りして、送ってくださったのです。
熊本地震で家を失い、全財産をなくした方もいました。避難所では肩身の狭い思いをしながら、それでも「この子だけは」と、愛するペットと共に避難してきた飼い主さんたち。他の被災者の方に遠慮して車中泊を続けていた人慣れしていないわんちゃんの飼い主さん。
その手には、愛するわんちゃん、ねこちゃんの姿が温かく刻まれた、世界に一つだけのキーホルダーが握られていました。キーホルダーを受け取った飼い主さんたちの、嬉しそうな表情は、今も鮮明に思い出すことができます。
これは単なる物資支援ではありません。すべてを失い、不安とストレスを抱える飼い主さんたちの心に深く寄り添う、「心のケア」としての支援でした。災害時のペット支援は、ただ動物の命を救うだけでなく、その動物を家族として愛する「被災者」である飼い主さんの心を支えることなのだと、改めて強く、強く感じさせられた瞬間でした。
「災害時のペット支援」は「動物愛護活動」ではありません。それは「被災者支援」そのものです。
「益城町わんにゃんハウス」の教訓と、私たちが目指すペット防災
数字で見る活動の軌跡
2016年5月から約4ヶ月間という短い期間でしたが、「益城町わんにゃんハウス」は、閉鎖までの199日間で、延べ43家族、犬38頭、猫19頭が入居しました。この数字は、ペットとの同行避難がいかに切実な課題であったかを物語っています。 益城町わんにゃんハウスでの経験は、災害時におけるペット支援のあり方について、多くの重要な教訓を与えてくれました。
最大の教訓は、支援の視点を「動物愛護」から「被災者支援」へと転換することの重要性です。ペットは家族の一員であり、そのペットを失うこと、あるいはペットと共に困難な避難生活を送ることは、飼い主にとって計り知れない精神的負担となります。動物を保護することと同時に、飼い主の心のケア、そして飼い主自身が主体的にペットとの生活を再建していくためのサポートが不可欠なのです。
そして、その支援は、特定の専門団体だけが担うものではありません。わんにゃんハウスが示したように、学生や個人、専門技術を持つ人々など、多様なバックグラウンドを持つ人々が、それぞれの知識や経験、そして何よりも「被災した人々の力になりたい」という純粋な思いを結集させることで、よりきめ細やかで、心に響く支援が生まれます。
その為にもわたしたちは災害時のペット支援が被災者支援であることを強く認識しなければならないのです。動物だけの支援ではなく、被災者支援であるならば支援する側に「出来る事」が多くなり、当然支援の輪は拡がります。
そしてわんにゃんハウスの様に、行政、施設管理者、専門家、多様なボランティア、そして何よりも被災した飼い主自身が固く連携し、それぞれの責任と役割を果たすこと。これこそが、困難な状況を乗り越え、ペットと共に生きる希望を繋ぐための鍵となります。
「災害時のペット支援」は「被災者支援」であり、「動物救済」ではない。それが結論です。
わたしたちペット防災ネットワークが目指すペット防災は被災者支援としてのペット支援です。
具体的なペット防災が学べるセミナーはこちら https://petbousai.jp/seminar