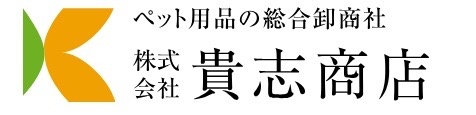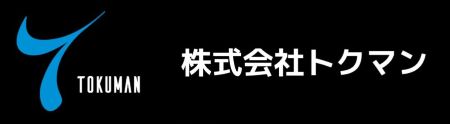動物取扱事業者はペット防災の最前線!日常の「適正飼育」啓発がペットの命を救う

はじめに:社会を支える「動物のプロ」の大きな責任
大切なペットと暮らす上で、そして社会全体で動物福祉を考える上で、「動物取扱事業者」の果たすべき役割は非常に大きいと言えます。それは、単にサービスを提供するだけでなく、飼い主と動物、双方の幸せに深く関わる社会的な責任を担う存在だからです。
トリミングサロン、ペットホテル、ペットショップ、動物病院、ドッグトレーナー。これらの「動物のプロ」たちは、飼い主にとって最も身近で、信頼できる相談相手です。そして、その専門的な知見と経験を活かした日々の活動こそが、動物福祉の向上、さらには災害からペットの命を守る「ペット防災」の礎となるのです。
ある保護犬とトリマーたちの物語から見る「プロの責任」
私が勤めていた会社での出来事です。そこには、トリマーさんが保護した繁殖引退犬や迷子犬が数頭いました。その中の一頭、ダックスフンドの「Qちゃん」は、会社の近くで保護された迷子の犬でした。
すぐに地域の動物愛護センターに連絡し、飼い主情報を照会しましたが、残念ながら飼い主は見つかりません。それからというもの、Qちゃんは会社のトリマーさんたちが愛情を込めて世話をすることになりました。人懐っこいQちゃんは、スタッフだけでなく、お店を訪れるお客様にとっても癒やしの存在となり、皆から愛される看板犬のような存在になっていきました。
月日が流れたある時、長年愛犬のトリミングで通ってくださっているお客様から、「ぜひQちゃんを家族として迎えたい」という、非常に温かい申し出がありました。
長年連れ添い、深い愛情を注いできたトリマーさんたちにとって、それは断腸の思いであり、苦渋の選択でした。しかし、「Qちゃんがより家庭的な環境で、特定の家族からの愛情を一身に受けて暮らせるのなら、それが一番の幸せではないか」と考え、譲渡を前向きに検討し始めました。
その時、彼女たちの取った行動は、まさに「動物のプロ」そのものでした。
Qちゃんが保護された経緯、詳細な性格や気質、日々の健康状態、既往歴、好きなこと、苦手なこと。そして、譲渡希望者さんの家族構成や生活環境、先住犬との相性など、考えられるあらゆる情報を網羅した詳細な文書を作成し、希望者の方へお渡ししたのです。
それは単なる情報の羅列ではありませんでした。そこには、Qちゃんへの深い愛情と、「新しい環境で絶対に幸せになってほしい」という切なる願いが、痛いほどに込められていました。
普段、保護譲渡を専門に行っている「保護ボランティア」ではない彼女たちが、ここまで徹底した対応をされたことに、私は「さすが動物のプロだ」と深く感銘を受けました。これこそ、命を預かる者としての責任感、そして動物と真摯に向き合う姿勢の表れです。
「最高の啓発の場」としての動物取扱事業者
私は幸いなことに、福岡市と熊本市で動物取扱責任者研修の講師を務める機会をいただきました。そのセミナーで、私が最も強く訴えたのは、まさにこの「動物のプロ」である動物取扱事業者が担うべき社会的責任の大きさと、その根幹となる「適正飼育の普及啓発」の重要性です。
考えてみてください。動物取扱事業者の店舗や事業所が、その専門知識と経験を活かして適正飼育の重要性を飼い主へ的確に伝え続けることができれば、それは実質的に「動物取扱事業者の数だけ、地域に動物愛護センターが存在する」のと同じくらいの啓発効果を生む可能性を秘めているのです。
動物愛護センターが担う大きな役割の一つに、地域住民への啓発活動がありますが、すべての飼い主が頻繁にセンターを訪れるわけではありません。むしろ、飼い主が日常的に接する機会が圧倒的に多いのは、近所のトリミングサロンやペットショップ、かかりつけの動物病院といった動物取扱事業者です。
つまり、動物取扱事業者の現場こそが、飼い主とペットの双方と直接向き合い、継続的に関係性を築ける「最高の啓発の場」となり得るのです。
適正飼育の普及こそが、最大の社会貢献であり「ペット防災」
この「最高の啓発の場」で、プロの視点から適正飼育に関する正確な情報やアドバイスを提供し続けること。これこそが、動物取扱事業者の最も重要な使命であり、社会貢献に他なりません。
そして、この「適正飼育の普及啓発」は、近年その重要性が叫ばれる「ペット防災」と直結しています。
ペット防災の基本は、決して特別な備えをすることだけではありません。その根幹にあるのは、「飼い主による日頃からの適正飼育」です。これを一番近くで、そして継続的に啓発できるのが、動物のプロである動物取扱事業者なのです。
健康管理と清潔の保持: 定期的なトリミングやグルーミングは、単に見た目を美しくするだけではありません。被毛を清潔に保ち、皮膚の状態を確認することは、避難所での共同生活における最低限のマナーです。
基本的なしつけ: 「待て」「おいで」などの基本的なこと、無駄吠えの抑制、そしてケージやキャリーケースに慣れさせておく「クレートトレーニング」。これらはすべて、災害時のパニックを防ぎ、安全な同行避難を実現するために不可欠です。ドッグトレーナーさんは、普段のトレーニングの中に防災の視点を組み込み、その重要性を伝えることができます。
これらの「適正飼育」が実践できていれば、災害という非日常においても、ペットは心穏やかに、そして周囲に迷惑をかけることなく過ごせる可能性が格段に高まります。
日常業務に織り込むペット防災の視点
動物取扱事業者は、ペット防災のために何か特別な活動に新たに取り組む必要はありません。普段の仕事の中に、ほんの少し視点を加えるだけでいいのです。
トリミングサロンでは: カットやシャンプーの際に、「災害時は数日間お風呂に入れないかもしれないから、定期的なケアで清潔を保つのは大事ですよ」と伝える。
ドッグトレーナーは: しつけ教室で、「この『ハウス』の練習は、避難所で静かに過ごすための最高の訓練になります」と目的を明確にする。
ペット用品販売店では: 店内に「ペット防災グッズコーナー」を設け、日常使いできるフードのローリングストック法や、携帯トイレなどを提案する。
動物病院では: 定期健診の際に、持病の薬の備蓄や、カルテのコピーを保管しておくことの重要性をアナウンスする。
このように、ペット防災は災害への「特別な備え」ではなく、「日頃からのペットとの向き合い方の延長線上にあるもの」です。そのことを、飼い主に最も近い専門家として伝え続けること。それこそが動物取扱事業者にしかできない、極めて重要な役割なのです。
業界の未来を拓くために
動物取扱事業者の現状はどうでしょうか?「適正飼育」に基づいた内容でしょうか?薄利多売、売れればいい、そんな状況ではないでしょうか?
今のまま「適正飼育」の重要性を軽視し、短期的な利益のみを追求する「薄利多売」のビジネスモデルに終始していては、動物取扱業界に明るい未来はありません。むしろ、知識と意識が高い飼い主からの信頼を失い、業界全体の衰退を招きかねません。
しかし、逆もまた然りです。
動物取扱事業者が一丸となって「適正飼育」の啓発に取り組めば、社会に素晴らしい好循環が生まれます。
飼い主に「適正飼育」の意識が浸透すれば、子犬を迎えた初期の段階から、プロであるドッグトレーナーにお金を払い、動物の習性や正しい接し方を学ぶことが当たり前になるでしょう。
定期的なトリミングは、単なる美容目的だけでなく、健康チェックの機会として認識され、利用回数が増えるはずです。
ペットの健康管理に対する意識も高まり、予防医療を含め、動物病院へ適切なタイミングで足を運ぶことが習慣化されます。
フード選びにおいても、安価なものを安易に選ぶのではなく、獣医師やペット栄養管理士のアドバイスを受け、個々の状態に合ったプレミアムフードを選ぶ飼い主が増えるに違いありません。
質の高いサービスを提供し、適正飼育を啓発し続けること。それが結果として顧客からの絶大な信頼を得て、動物取扱事業者自身の健全な発展、そして業界全体の地位向上に繋がっていくのです。
結論:すべての根底にある「動物への揺るぎない愛情」
最後に、あのダックスフンド「Qちゃん」の話に戻ります。
トリマーさんたちの熟慮の末、Qちゃんは外部に譲渡されることなく、最終的には一人のトリマーさんの家庭に正式に迎えられました。家族の一員として、たくさんの愛情に包まれ、穏やかで幸せな日々を送り、昨年、その一生を全うしました。
私は、Qちゃんを愛情深く世話してきたトリマーさんたちの姿から、多くのことを教えてもらいました。「動物のプロとしての知識と倫理観、そして自覚」もさることながら、最も心に刻まれたのは、やはり彼女たちの行動の根底に常にあった「動物たちへの揺るぎない愛情」でした。
これこそが、動物に関わる全ての仕事において、最も大切にすべき原点なのだと、改めて強く感じています。
動物取扱事業者の皆様一人ひとりが、その愛情を胸に、専門家としての社会的責任を果たしていくこと。その先に、動物も人も、災害時でさえも安心して暮らせる社会があると、私は信じています。