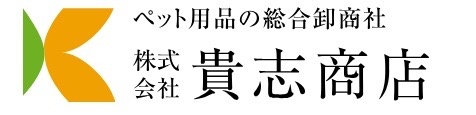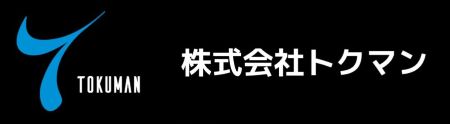なぜ川口市はペット同行避難は「原則屋内」市民の声が地域防災計画を変えた

はじめに:ペット防災を学ぶ中で得た気づきと転機
以前に、「ペット防災に取り組むきっかけ・日ごろ感じていること」についてのコラムを書かせていただきました。今回は、ペット防災を学んでいる過程で得た気づきと、訪れた転機についてのお話になります。
個人的な感覚と経験によるものではありますが、どなたかにとって何かお役に立つことがあればと思い書かせていただきます。最後までお読みいただけると嬉しいです。
【気づき①】市の計画と現場のギャップ、そして住民座談会へ
私が住んでいる埼玉県川口市では、危機管理課様が作成している『防災本(川口市防災ハンドブック)』を市が無料配布してくださっています。その中の「避難所開設と運営管理」のページに、ペット同行避難についての記載があります。
情報を更新しながら作成されていて、私がペット防災を勉強し始めた令和元年(2019年)には既にペット同行避難について、「市内の指定避難所である小・中・高等学校には、ペットと避難することができます」と書かれていました。しかし、当時の現場の実情は対応者の判断に委ねられているケースもあり、ペットを連れての避難を断られたという経験談を聞いたこともありました。
大前提として、災害時にペットを連れて避難する場所は、必ずしも避難所である必要はありません。自宅でも車でも安全に身を寄せられるのであればいいのですが、もしも火災が起きたら?もしも車の鍵が見つからなかったら?どうしても避難所以外に選択肢がなかったら?
発災時に全ての避難所が開設されるとは限らないのに、市内でペット同行避難の考え方がバラバラでは、いざという時に住民が混乱すると感じました。なにより、それでは私自身が路頭に迷う姿が想像できました。市内90か所の指定避難所運営者にペット同行避難について考えを揃えていただくためにはどうしたらよいのかわからず、1か所ずつ説明して歩こうかとも考えました。しかし、1人で全てを巡るのでは時間がかかり過ぎてしまいます。
地域に1人ずつでもペット同行避難について啓発をしてくれる仲間ができないだろうかと方法を模索していたところ、福祉総務課様が市を20地域に区割りして住民座談会を開催している最中で、地域ごとに参加者を募集していることを知りました。地域住民の顔の見えるつながりを育み、地域の困りごとや必要な仕組みなどを抽出することを目的とした座談会で、私は自分の住まいがある地域以外にもできるだけ参加をさせていただきました。その中でタイミングがあれば、ペット同行避難について地域の皆さんで考えてみてほしいという話もさせていただくことができました。
【気づき②】ペットは最優先事項ではない。地域社会の「当たり前」を知る
2年ちかく住民座談会に参加させていただいているうちに、私にとって重要な「ペット」というキーワードは、多くの人にとっては最優先事項ではないということが見えてきました。地域の困りごとを話し合う場にペットの問題を主訴として来る人はいませんでした。
問題に上がるのは、高齢化に起因すること、地域のつながりの希薄さに関すること、子育て、障害、孤立、あったらいいなと感じている施設や取り組みなど、実に様々で、どれも地域の皆様にとって深刻で重要な内容でした。そして、それらの問題を抱えていらっしゃる方々の中にペット飼育者も含まれているのです。さらに、住民構成や地形なども作用し、地域によって課題の特色が違うことを知ることができました。
災害時にペットのことは後まわしになるというような話を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、それは災害時に限ったことではなく、単に日常の延長なだけなのです。まずは人の問題が解決できなければ、誰も他人のペットのことには意識がまわらないのです。
そして、同じ市内であっても地域ごとに抱えている問題に違いがある。それが普通の社会なのだと理解しました。意識している・していないに関わらず、人の暮らしの中にペットは当たり前に存在しているからこそ、ペット同行避難だけを切り口にしているだけでは普及啓発が進まないのだと感じたこの経験から、私は自分なりに啓発活動の方向性が見えてきたように感じました。
【転機】地域防災計画の全面改訂と、声を届けたパブリックコメント
先述の経験のおかげで、人の福祉と危機管理はつながっていることと、人の暮らしが安心安全でなければペットのことは後まわしになることが、私の中で明確に腑に落ちる感覚がありました。そのころに、市のペット同行避難に関する方向性を一つにするために重要な転機が訪れました。川口市地域防災計画が10年ぶりに全面改訂されたのです。
地域防災計画は、災害対策基本法に基づくものです。地域で災害が起きた時に、誰が・何を・どうするかを決めておく計画を、地域の実情に合わせて各自治体が作成しています。
全面改訂の前に、川口市地域防災計画(案)に対するパブリックコメントの募集があり、私はペットについての意見を提出させていただくことにしました。本編およそ390ページ、資料編およそ221ページの全てを漏らさず目を皿のようにして読み、ペットに関することも記述が必要ではないかと感じた部分を指し示し、7か所について追記を求める意見を提出しました。
提出書類の書き出しには、
「地域防災計画にペットについて明確な記載を増やしておくことは、ペット飼育者を優遇するためのものではないこと」
「ペットを飼っている・いないにかかわらず災害時に起こるペットの問題について地域で考えていただくことにつながると思うこと」
「ペット同行避難の対策が十分でなければ、飼育者の災害関連死の危険が高まること」
「ペットの命を守ることは人命を守ることにつながっていること」
など、ペットに関する追記が地域全体に関する決まり事として必要だと感じる理由も添えました。
そして、以下3か所に追記がされ、運用が開始されました。
①ペット専用の避難スペースの確保(避難所等の運営体制の整備)
②被災動物の支援に関する情報(市民の生活安定に必要な広報)
③ペットスペースを原則屋内に区割りし、ペット専用のスペースを設置する(避難所の運営体制の確立/居住区域割り振りの留意点)
特筆すべきは③の避難所でのペットスペースが「原則屋内」という部分です。市民の暮らしや安全を脅かす緊急事態に備えて対策を担うスペシャリストたちが、高い見識を基に総合的に判断してくださったのだと捉えています。
実現した「原則屋内」―これからの目標
私はペット防災の勉強と活動から、いくつもの学びと気付きを得てきました。自分は地域の一員で、様々な関わりの中で生き、たくさんの人に助けられていることも感じることができるようになりました。自分の愛猫を災害時でも守りたい一心で始めたことですが、こんなにたくさんのことに気づかせてくれた愛猫たちを改めてよりいっそう大切に感じています。
だからこそ、一つ一つの命が尊重され、守られるための取り組みが進んでほしいし、ペットが困りごとになる社会ではあってほしくありません。これからの目標は、地域防災計画に記載されているペット同行避難に関する市の方針を地域に拡めていくことです。日常から災害時までペットが困りごとにならない社会づくりのために、勉強と活動を続けていきたいと思います。
人とペットの防災クラブ/川口市動物愛護推進員 近江和子