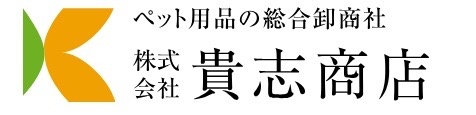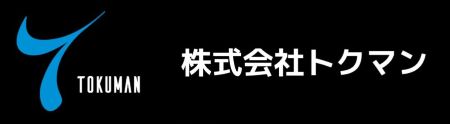【大型犬のペット防災】避難所に入れない?熊本地震の教訓から学ぶ、愛犬と生き抜くための現実的な備え

はじめに:災害時、本当にペットと「同行避難」できますか?
大好きなペットと共に避難所へ向かう「同行避難」。それは、災害時にペットを飼う全ての人が願う、当たり前の行動です。しかし、その当たり前が、現実には非常に困難な壁に阻まれることがあります。
特に、体が大きく存在感のある「大型犬」と共に避難するとなると、その難易度は格段に上がります。
私たちが活動の拠点とする熊本で発生した2016年の熊本地震。あの時、多くの避難所が開設されましたが、その中で大型犬の姿を見ることはほとんどありませんでした。これは、決して大型犬の飼い主がペットを見捨てたわけではありません。「避難したくても、できなかった」「受け入れてもらえなかった」という、厳しい現実があったのです。
本記事では、熊本地震の経験を元に、なぜ大型犬の同行避難が難しいのか、そして、その困難な状況の中で愛するペットと自分自身の命を守るために、飼い主が今から何をすべきなのかを、具体的に掘り下げていきます。
第1章:なぜ大型犬の「同行避難」は難しいのか?熊本地震の教訓
災害時の同行避難は、ペットの種類や大きさによって直面する課題が大きく異なります。中でも大型犬は、小型犬とは比較にならないほどの困難が伴います。
避難所における物理的なスペースの問題
まず直面するのが、圧倒的なスペースの問題です。体育館などの指定避難所は、一人でも多くの被災者を受け入れるため、一人当たりのスペースは非常に限られています。その中で、大型犬が安心して過ごせる大きさのケージやクレートを置く場所を確保することは、物理的にほぼ不可能です。
熊本地震の際も、避難所運営側が大型犬用の屋外ケージを用意していたというケースは皆無でした。多くの人が混乱し、心身共に疲弊している中で、特定のペットのために特別なスペースを用意する余裕は、残念ながら現場にはないのが実情です。
周囲への影響と見えない「心理的な壁」
次に、他の避難者への配慮という大きな壁が立ちはだかります。避難所には、動物が苦手な人、アレルギーを持つ人、そして災害のストレスで精神的に非常に敏感になっている人が大勢います。
大型犬は、その大きさだけで周囲に威圧感や恐怖心を与えてしまうことがあります。また、鳴き声や匂い、トイレの問題も、体が大きい分、より深刻な問題として捉えられがちです。「周りに迷惑をかけてしまう…」という飼い主自身の強いプレッシャーが、避難所へ足が向かない大きな原因となるのです。
熊本地震で見た現実:屋外係留と自宅への取り残し
では、避難所に入れなかった大型犬や、普段から外飼いされている中・大型犬はどうしていたのでしょうか。熊本地震で私たちが目にしたのは、胸が痛む光景でした。
避難所の外での係留: 避難所の片隅の柱や木に、リード一本で繋がれている犬たち。雨風や強い日差しを遮るものもなく、絶えず人や車が行き交う不安な環境で、飼い主を待ち続けていました。衛生状態も悪化しやすく、ストレスから体調を崩す犬も少なくありません。
被災した自宅への取り残し: 飼い主だけが避難所に身を寄せ、犬は倒壊の危険がある自宅や庭に残されるケースも多く見られました。余震の恐怖、食料や水の不足、そして何より飼い主と離れた寂しさと不安。これは、犬にとって非常に過酷な状況です。
これらは、飼い主の愛情が足りなかったからではありません。他に選択肢がなかった、というのが偽らざる現実だったのです。
第2章:「自宅に残る」は安全か?指定避難所へ行くことの重要性
「避難所でそんな思いをさせるくらいなら、私はあの子と一緒に家に残る」 そう決意する飼い主さんは少なくありません。その気持ちは痛いほど分かります。しかし、その選択が、かえって飼い主とペット双方を危険に晒し、未来を困難にする可能性があることを知っておかなければなりません。
被災した自宅に潜む「生命の危機」
最も懸念すべきは、二次災害による「生命の危機」です。一度大きな地震が起きると、本震と同等、あるいはそれ以上の規模の余震が何度も発生する可能性があります。被災した家屋は非常に脆くなっており、僅かな揺れで倒壊する危険性があります。
また、地震だけでなく、台風や豪雨による土砂災害、河川の氾濫、津波など、災害の種類は様々です。ライフラインが寸断され、火災が発生するリスクもあります。安全だと信じていた自宅が、最も危険な場所になり得るのです。
避難所で得られる公的な「支援」と「情報」
指定避難所へ避難する最大のメリットは、命を守るための「公的支援」と「正確な情報」を迅速に受けられることです。
支援物資: 食料、飲料水、毛布、衛生用品といった生きるために不可欠な物資が届けられます。近年では、ペットフードやトイレシートなどのペット用支援物資が届くことも増えてきました。
正確な情報: 災害の状況、給水・炊き出しの場所、インフラの復旧見込み、支援制度の案内など、生活再建に必要な情報が集まります。
医療とケア: 医師や保健師が常駐し、ケガの治療や健康相談、心のケアを受けることができます。
指定避難所に行かなければ、これらの支援や情報から取り残されてしまいます。それは飼い主自身の心身を追い詰め、生活再建を遅らせることに繋がります。そして、飼い主の困窮は、最終的に愛犬の生活環境にも深刻な影響を及ぼすのです。
飼い主の再建が、ペットの未来を守る
当然ですが、災害時にはまず飼い主自身の安全と生活の安定を確保することが最優先です。飼い主が心身ともに健康でなければ、ペットを守り続けることはできません。まずは飼い主が公的な支援を受けられる場所に身を置き、一日も早く生活を立て直すこと。それが、結果的に愛するペットとの穏やかな日常を取り戻すための、最も確実な道筋となるのです。
第3章:今すぐ始めるべき!大型犬の飼い主ができる具体的な備え
行政の対策にも限界があります。最終的に愛犬を守れるのは、飼い主自身です。困難な状況を乗り越えるために、平時からできる備えは数多くあります。
【住環境の見直し】「室内飼育」が同行避難の成功率を上げる
もし現在、大型犬を外飼いしているのであれば、室内飼育への移行を真剣に検討してください。災害時にパニックになった犬が繋がれたリードを引きちぎって逃走するケースは後を絶ちません。普段から家族と共に室内で過ごすことで、犬は安心感を得られ、災害時にも飼い主の側で落ち着いて行動しやすくなります。
【選択肢の確保】愛犬の命を繋ぐ「預け先」という選択肢
同行避難が理想ですが、それが叶わない場合に備え、複数の避難先を確保しておくことが極めて重要です。
親戚・友人宅: 大型犬の飼育に理解があり、受け入れを承諾してくれる親戚や友人を、複数探しておきましょう。災害時には相手も被災している可能性があるため、必ず複数の候補を見つけておくことが大切です。
かかりつけの動物病院: 災害時の受け入れ体制について、事前に相談・確認しておきましょう。
ペットホテル・一時預かり施設: 自宅から少し離れた、被災する可能性が低いエリアの施設もリストアップし、いざという時の受け入れについて確認しておくことをお勧めします。
愛犬と離れることは、飼い主にとって断腸の思いでしょう。しかし、熊本地震の現実を見て痛感したのは、「一時的に離れる」という苦渋の決断が、結果として双方の命と未来を守る最善の策になり得るということです。全ては、一日も早く愛犬と元の暮らしを取り戻すため。その覚悟を持つことも、飼い主の愛情の一つです。
まとめ:今、大きな災害が起きたら?真剣に考えることが、命を守る第一歩
災害は、いつ、どこで、どのような形で私たちを襲うか分かりません。「うちは大丈夫」という根拠のない楽観は捨て、いずれにしても飼い主が災害時にどうするのかを考える事。
今、大きな災害が起きたら?
真剣にそう考えてみる事が大切です。これは大型犬、小型犬関係なくペット防災の基本中の基本です。
災害を「じぶんごと」として考える事が出来なければ、災害への備えは出来ません。
もちろん、大型犬だからと、同行避難を諦める必要はありません。しかし、その困難さを正しく理解し、現実的な選択肢をいくつも用意しておく必要があります。ご近所付き合い、そして具体的な避難計画。それら一つ一つの「そなえ」の積み重ねが、あなたと、あなたの愛する家族の命を守る唯一の道筋です。
この記事をきっかけに、ぜひご自身のペット防災計画を見直してみてください。私たちのセミナーでは、さらに具体的な事例や対策についてもお話ししています。大切な家族を守るために、今日から行動を始めましょう。