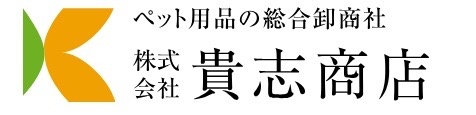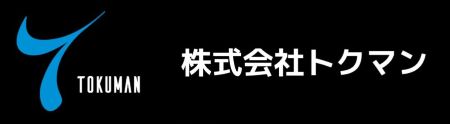「ガイドラインでしょ?」では済まされない。自治体がペット防災に取り組むべき根拠

はじめに:ある自治体職員の一言から考える
『災害時のペット対策についてですが、環境省のガイドラインは、あくまで”ガイドライン”ですよね?』
これは、わたしがある自治体でペットの災害対策セミナーについての講演を行った際の質疑応答の中で、ある自治体の危機管理課職員の方から実際に投げかけられた言葉です。
わたしはこの言葉の裏に「ガイドラインは所詮ガイドラインであって努力目標にしか過ぎない、法的拘束力はありませんよね?」そんな思考を感じ取りました。
これは決して特別な意見ではなく、残念ながら多くの自治体で聞かれる声でもあります。こうした発言の背景には、縦割り行政の中で防災担当部署が動物愛護行政に関わる機会が少ないことや、ペットの問題が「個人の趣味」の領域であるという根強い誤解が存在します。
しかし、大規模災害時においてペットの問題は、飼い主個人の問題に留まらず、地域社会全体の安全や公衆衛生、ひいては人命に関わる重大な「防災マター」となります。
確かに「ガイドライン」という言葉だけを聞けば、努力目標や参考資料といった程度の認識を持たれてしまうかもしれません。しかし、こと災害対策、特にペットとの同行避難に関しては、その認識は大きな誤解であり、過去の災害の大切な教訓を軽視することに繋がりかねません。
なぜ、自治体は災害時のペット支援を行う必要があるのか。それは決して単なる努力目標ではなく、「防災基本計画」「動物愛護管理法」そして「環境省ガイドライン」という、相互に連携した明確な根拠に基づく、自治体の重要な責務だからです。
今回の記事では、この3つの関係性を丁寧に紐解きながら、なぜ「ガイドラインだから」の一言で済ませてはならないのか、その本質的な理由を詳しく、そして深く解説します。
すべての基本となる「国の防災基本計画」とは
まず、日本の防災体制の根幹をなす「防災基本計画」について理解する必要があります。
■過去の教訓から進化し続ける、日本の防災の礎
防災基本計画は、決して固定化された文書ではありません。阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震そして記憶に新しい能登半島地震など、我が国が経験してきた数多の災害の教訓を糧に、これまで30回近くも改定が重ねられてきた、いわば日本の防災対策の歴史そのものです。
この計画は、災害対策基本法第34条に基づき、中央防災会議が作成する、日本の防災分野における最上位の計画です 。これは、国、地方公共団体、そして指定公共機関などが、それぞれの立場で防災計画を作成したり、防災業務を遂行したりする際の「大本の方針」を示す、いわばマスタープランとしての役割を担っています 。
つまり、都道府県や市町村が策定する「地域防災計画」は、この国の防災基本計画に矛盾・抵触してはならないとされており、計画に書かれている内容は、そのまま地域レベルでの具体的な計画に落とし込まれるべき、極めて重要な指針なのです。
防災基本計画におけるペット関連の記述の重要性
かつて、この最上位計画にペットに関する明確な記述はありませんでした。しかし、大きな転機となったのが2011年の東日本大震災です。ペットを屋内に残したまま避難し、結果として多くのペットが命を落としただけでなく、ペットを案じるあまりに飼い主自身の避難が遅れたり、避難所への受け入れを拒否されて車中泊を余儀なくされたりと、ペットにまつわる問題が人命や被災者の健康に関わる深刻な課題として浮き彫りになりました。
これらの重い教訓を受け、防災基本計画にはペットに関する重要な記述が盛り込まれました。防災基本計画の中には「同行避難」を前提とした国の方針が以下の通り明確に示されています。
①【平時】飼い主の備え(自助)を促す記述 まず、災害への備えの段階で、国民が平時から行うべきこととして、ペットとの同行避難の準備が求められています。
【第2編 第1章 第3節 2 (1) 防災知識の普及】 ・「最低3日間、推奨1週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備、自動車へのこまめな満タン給油、負傷の防止や避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策、飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所等での飼養についての準備、保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等の家庭での予防・安全対策
これは、国が国民(飼い主)に対し、災害時にはペットと共に避難すること(同行避難)を前提として、そのための準備をしておくよう促していることを意味します。
②【災害時】自治体の対応(公助)を定める記述 そして、災害が発生し、飼い主が平時の備えのもとでペットと同行避難してきた場合、市町村はそれを受け入れる責務があることを定めています。
【第2編 第2章 第6節 避難の受入れ及び情報提供活動】 ○市町村は、指定緊急避難場所や避難所に家庭動物と同行避難した被災者について、適切に受け入れるとともに、避難所等における家庭動物の受入状況を含む避難状況等の把握に努めるものとする。
【第2編 第2章 第6節 避難の受入れ及び情報提供活動】
市町村は、必要に応じ、被災者支援等の観点から指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。
このように国の防災基本計画には災害時の飼い主とペットの同行避難を前提とした「飼い主」「自治体」の役割が明記されています。これは、自治体がペット防災に取り組むべき、最も強力な計画上の根拠と言えるでしょう。
もう一つの法的根拠「動物愛護管理法」
防災基本計画と並び、自治体のペット災害対策を支えるもう一つの重要な柱が「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」です。
この法律は、第1条で「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」と共に、「人と動物の共生する社会の実現を図る」ことを目的としています。この「人と動物の共生」には、当然ながら災害時のような非常時も含まれます。
■法律で定められた自治体の責務
動物愛護管理法では、国が「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(基本指針)」を定めること(第5条)、そして都道府県がその基本指針に即して「動物愛護管理推進計画」を定めること(第6条)が義務付けられています。
そして、この「基本指針」の中に、災害対策に関する項目が含まれているのです。
災害時における動物の適正な飼養及び保管に関する施策に関する事項 災害時において、平常時から所有者等による備えを促すとともに、関係機関・団体等と連携した動物の避難、保護、収容及び適正な飼養保管を図るための対策を推進する。
これにより、都道府県が策定する「動物愛護管理推進計画」には、災害対策を盛り込むことが必須となりました。つまり、動物愛護行政の観点からも、自治体はペットの災害対策を行う法的な責務を負っているのです。
これは、福祉保健局や環境生活部といった、いわゆる「動物愛護担当部署」だけの話ではありません。防災担当部署である危機管理課も、当然ながらこの法律と計画を遵守し、関係部署と連携して対策を進める義務があります。
法と計画を繋ぐ実践書「人とペットの災害対策ガイドライン」
ここまで見てきたように、自治体にはペット防災に取り組むべき明確な計画上・法律上の根拠があります。
防災基本計画:同行避難の準備と受け入れ体制を整備せよ(WHAT)
動物愛護管理法:災害時の動物の避難・保護体制を計画し、推進せよ(WHAT)
これらは、自治体が「何をすべきか(WHAT)」という大きな方針を示しています。しかし、では「具体的に、どのようにすれば良いのか(HOW)」という現場レベルでの疑問が残ります。避難所のどこにペットを置くのか、アレルギーを持つ避難者への配慮はどうするのか、必要な物資は何か。
その「HOW」に詳細に答えるために作られたのが、環境省の「人とペットの災害対策ガイドライン」なのです。
このガイドラインは、防災基本計画や動物愛護管理法に示された方針を、自治体や飼い主、そして関連事業者が具体的に実行するための、いわば「公式な実践マニュアル」と位置づけることができます。法や計画が人体の「骨格」だとすれば、ガイドラインは実際に体を動かすための「筋肉や神経」にあたります。
つまり、「防災基本計画」と「動物愛護管理法」という2つの法的・計画的な根拠と、それらを実行するための具体的な方法を示した「ガイドライン」は、三位一体となって初めて機能します。どれか一つでも欠けてはならず、ガイドラインを「単なる参考資料」と軽視することは、計画や法律の趣旨そのものを形骸化させてしまうことに繋がるのです。
机上の空論ではない。血の通ったガイドライン策定の現場
環境省のガイドラインもまた、防災基本計画と同様に、過去の災害現場の厳しい現実から生まれました。
私自身、2016年の熊本地震の際、環境省との協働プロジェクトの現地責任者として活動しましたが、その策定過程を目の当たりにしました。環境省の職員の方々は熊本に常駐し、避難所を一つひとつ回り、飼い主、支援者、そして自治体の担当者一人ひとりに、粘り強く聞き取り調査を行っていたのです。
熊本地震では、ペットがいることを理由に避難所に入れず車中泊を選び、エコノミークラス症候群で命を落とすという痛ましい二次災害が発生しました。また、避難所内ではペットの鳴き声や臭い、動物アレルギーを持つ避難者とのあつれきなど、住民間のトラブルまあり、多くの課題が浮き彫りになりました。
こうした現場の課題一つひとつに対応するため、ガイドラインは改訂されました。例えば、車中泊による健康被害の多発という教訓から、ガイドラインでは在宅避難者や車中泊避難者への支援の重要性が明記されました。避難所でのトラブルという教訓からは、ペットの飼育スペースと一般の居住スペースを分ける「ゾーニング」の考え方や、衛生管理の方法が具体的に示されました。
つまり、これらの指針は決して机上の空論ではなく、「過去の被災地での現実の検証」という血の通った経験に基づく、災害対策の道しるべなのです。
結論:過去の教訓を未来へ繋ぐために
災害対策の基本は、常に「過去の災害の検証」にあります。 なぜ被害が拡大したのか。何が足りなかったのか。どうすれば次の災害で同じ悲劇を繰り返さずに済むのか。この問いを突き詰めるプロセスこそが、防災の本質なのです。その検証の結果が、法改正や「防災基本計画」の改定に繋がり、そして具体的な行動指針である「ガイドライン」として体系化されてきました。
したがって、自治体職員が「ガイドラインだから」という言葉でその重要性を軽視することは、熊本地震や東日本大震災などの被災地の経験と教訓を無視することに他なりません。
被災経験がない自治体の担当者の方にこそ、お願いしたいことがあります。これらの指針を、単なる計画策定のための参考資料として表面的にコピー&ペーストするのではなく、その背景にある一つひとつの教訓まで含めて深く受け止めていただきたいのです。そして、自分たちの地域でどのように具体化していくかを、真剣に考えていただきたい。それこそが、実効性のある対策への唯一の道だと、私たちは被災地での経験を通して確信しています。
私たちNPO法人ペット防災ネットワークは、ペット防災セミナーなどを通じて、飼い主さん一人ひとりの防災意識を高める活動を行っています。しかし、個人の備え(自助)だけでは乗り越えられないのが、大規模災害の現実です。行政による支援(公助)、そして地域コミュニティでの助け合い(共助)が一体となって初めて、尊い命を守ることができます。
自治体の担当者の皆様には、ぜひこの「防災基本計画」「動物愛護管理法」「環境省ガイドライン」の三位一体の関係性を正しくご理解いただき、すべての人が安心して避難できる地域づくりを主導していただくことを切に願います。
正しいペット防災の知識を得るためのペット防災セミナーはこちら