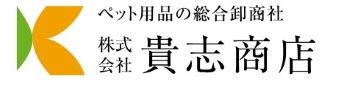ペット防災 理想の避難と、現実的な備え 二つの選択肢

はじめに:揺らぐ「同行避難」の原則と、私たちが示す道筋
「災害が起きたら、ペットと一緒に近くの避難所へ」
これは、国が示す「同行避難」の原則に基づいた、飼い主にとっての基本となる考え方です。しかし、残念ながら多くの自治体において、この原則を受け入れるための指定避難所の体制が十分に整っていないのが現状です。
その結果、多くの飼い主が「避難所に行けば何とかなるはず」という期待と、「本当に受け入れてもらえるのだろうか」という不安の狭間で、災害の時を迎えることになります。
私たちNPO法人ペット防災ネットワークは、この状況に強い危機感を抱いています。
私たちの最終的な目標であり、ペット防災における最善の策は、「指定避難所で、ペットが屋内で安心して過ごせる体制を確立すること」です。
しかし、その理想の実現にはまだ時間が必要です。だからこそ、過渡期である「今」、私たちは飼い主の皆様に、理想の未来を見据えつつ、現実的な自衛策として2つの選択肢を持つ「新・避難計画」を提唱します。
それは、「事前に調整済みの私的避難先(プラン A)」と「公的避難所(プランB)」という考え方です。この記事は、なぜ今この両輪の備えが必要なのか、そして私たちの目指す未来はどのようなものなのかを、皆様と共有するためのものです。
公的避難所の「理想」と「現実」
災害時、住民のために開設される公的避難所。しかし、ペット防災の観点から見ると、そこには大きな課題、つまり「理想」と「現実」のギャップが存在します。現在、多くの避難所では、仮に「ペット受け入れ可」であっても、以下のような課題に直面します。
屋外や共用部での飼育: 衛生面やアレルギーを持つ方への配慮から、ペットは体育館などの居住スペースに入れず、屋外の軒下や廊下でのケージ飼育を求められるケースが少なくありません。これはペットの心身に多大なストレスを与え、熱中症や低体温症のリスクも伴います。
トラブルのリスク: 鳴き声や臭いなどをめぐり、動物が苦手な他の避難者との間でトラブルが発生し、飼い主が肩身の狭い思いをする可能性があります。
不統一なルール: ペットの受け入れルールは自治体や各避難所の判断に委ねられており、災害の混乱下で受け入れ先を探すのは極めて困難です。
こうした現実は、飼い主とペットを心身ともに追い詰め、時には避難所での生活を諦め、危険な自宅や車中での生活を選択させてしまう「二次災害」の原因にもなりかねません。
私たちの目指す未来 – 熊本地震の教訓と「屋内同行避難」の重要性
しかし、私たちは公的避難所での受け入れを諦めているわけではありません。むしろ、その実現こそが私たちの使命です。なぜなら、その理想が実現可能であることを、私たちは過去の災害から学んでいるからです。
その最大の教訓が、2016年の熊本地震です。
当時、熊本市をはじめとする多くの避難所では、様々な工夫を凝らし、ペットと飼い主が同じ空間で過ごす「屋内同行避難」が実現されました。ロビーや空き教室などをペット同伴者専用スペースとして開放し、ルール作りを徹底することで、一般の避難者との共存を可能にしたのです。
この経験は、私たちに極めて重要なことを教えてくれました。それは、「ペットを家族」と考える飼い主にとって、離れ離れの避難は心身に深刻なダメージを与え、飼い主のストレスはペットにも伝染するということです。共にいる安心感こそが、過酷な避難生活を乗り越えるための何よりの支えとなるのです。
「同行避難を認める」と言いながらも「ペットは原則屋外」とされているような現状は同行避難の原則を形骸化させていて、飼い主の避難行動の遅れにも繋がり、「飼い主自身の安全を守る」という災害時のペット同行避難の本来の目的は果たせません。
この熊本地震での成功事例を「特別な例外」で終わらせず、全国のスタンダードとすること。それが、「ペット同行避難」の原則を有名無実化させないための、私たちNPO法人ペット防災ネットワークの責務です。私たちは、自治体や関係機関への働きかけを続け、屋内同行避難が当たり前になる社会を目指して、全力でその体制作りに取り組んでいきます。
だからこそ今、必要になる「自助」としての選択肢
私たちは、屋内同行避難の実現に向けて活動を続けます。しかし、その体制が全国津々浦々で整うには、まだ時間がかかります。
その未来が訪れるまでの間、私たちはただ待っているわけにはいきません。目の前で起こりうる災害から愛するペットの命を確実に守るために、私たち飼い主一人ひとりが「自助」の精神で、主体的に行動する必要があります。
そこで重要になるのが、冒頭で述べた「私的避難」という選択肢です。
私的避難という主体的選択
これは、被災想定区域外に住む親戚・知人宅や、ペット同伴可能な宿泊施設など、公的避難所以外に事前に確保した安全な場所へ避難する計画です。
この私的避難を選択肢として準備しておくことで、
避難所の受け入れ可否に一喜一憂せず、確実な避難先を確保できる。
ペットも飼い主も、精神的・肉体的ストレスの少ない環境で過ごせる。
他の避難者に気兼ねすることなく、落ち着いて生活の再建に臨める。
といった、計り知れないメリットが生まれます。これは、「誰かに助けてもらう」という受け身の姿勢から、「自らの判断と準備で、家族の安全を確保する」という、飼い主としての責任を果たすための、最も確実な行動なのです。
二つの避難計画の準備の徹底 プランAとプランB
「私的避難」という計画は、決して難しいものではありません。今日から始められる具体的なステップをご紹介します。
まずは、あなたの「私的避難ネットワーク」の候補となる場所を、思いつく限り書き出してみましょう。
親戚・友人リスト:自宅から離れた、被災想定区域外に住んでいる親戚や友人をリストアップします。
一人だけでなく、複数の候補を考えておくことが重要です。
宿泊施設リスト:「ペット同伴可 〇〇(地域名)」「ペットと泊まれる宿」などのキーワードで検索し、複数のホテルや旅館、民泊施設をリストアップします。
被災想定区域外にある施設を優先的に探しましょう。
専門施設リスト:日頃からお世話になっている、かかりつけの動物病院やペットホテルに、災害時の一時預かりが可能かどうかを確認します。関係性が構築できている場所は、いざという時に頼りになります。
【STEP 2】事前に「災害時の避難」について相談・交渉する
リストアップが完了したら、次は具体的な相談と交渉です。平時のうちに、必ず相手の承諾を得ておきましょう。
親戚・友人への相談:「もしも大きな災害が起きたら、ペットと一緒に一時的に避難させてもらえないか」と、率直に相談します。
その際、同居家族全員の同意が得られるか、アレルギーを持つ人はいないか、動物が苦手な人はいないかなどを必ず確認してください。相手の負担にならないよう、避難時のルール(ケージを持参する、ペットフードやトイレシートは全てこちらで用意するなど)を具体的に提示すると、相手も安心して受け入れやすくなります。
宿泊施設への確認:リストアップした施設に電話やメールで連絡し、「災害発生時に、ペット同伴での避難先として利用することは可能ですか」と問い合わせます。
確認すべきポイント:災害時の予約受付方法 受け入れ可能なペットの種類や大きさ、頭数
必要な持ち物(ケージ、ワクチン証明書など) 料金体系(緊急時の特別料金の有無など)
【STEP 3】プランB「公的避難所」を徹底的に調査する
プラン Aが盤石でも、何が起こるか分からないのが災害です。もうひとつの選択肢としてお住まいの地域の公的避難所について調べておきましょう。もちろん避難所の受入れ体制によってはPlan AとPlan Bが逆転する場合もあります。どちらのプランを優先するかを決める為にも事前の準備、調査が重要となります。
自治体のウェブサイトを確認:お住まいの市区町村の公式ウェブサイトで、「防災」「避難所」といったページを探します。「ペット同行避難」に関する方針や、同行避難可能な指定避難所のリストが公開されている場合があります。
防災担当課へ問い合わせる:ウェブサイトで情報が見つからない場合は、役所の防災担当課に直接電話で問い合わせます。
確認すべきポイント:ペット同行避難が可能な避難所はどこか? 飼育場所は屋内か屋外か?
受け入れに関する具体的なルールや条件は何か?(ケージのサイズ、必要な備品など)
得た情報は必ずメモに残し、家族で共有しておきましょう。
【STEP 4】命をつなぐ「避難経路」を複数確保する
避難先が決まっても、そこへ安全にたどり着けなければ意味がありません。自宅からそれぞれの避難先候補地(プラン Aおよびプラン B)までの避難経路を計画します。
ハザードマップの活用:まず、自治体が発行するハザードマップを見て、土砂災害や洪水などの危険箇所を把握します。
複数のルートを設定:危険箇所を避けるように、主要な道路を使うルート(車での移動を想定)と、道が寸断された場合を想定した代替ルート(徒歩での移動も考慮)を、最低でも2〜3通り考え、地図上に書き込んでおきましょう。
シミュレーションを行う:実際にそのルートを歩いたり、車で走ってみたりして、危険な箇所がないか、夜間でも安全か、ペットを連れて移動するのにどれくらいの時間がかかるかなどを体感しておくことが、いざという時の冷静な行動につながります。
まとめ:最高の備えは、主体的な計画から生まれる
本記事でお伝えしてきた「新・避難計画」の要点は以下の通りです。
「公的避難所に行けば何とかなる」という思い込みを捨てる。
信頼できる親戚・友人宅や宿泊施設など、「私的避難先」の確保のプランAと、地元の「公的避難所」のプランBの二つの選択肢を持ち事前に準備、調査しておく。そして各避難先までの安全な「避難経路」を複数確保しておく。
ペット防災は、グッズを揃えるだけで終わりではありません。どこへ、どのように避難するのかという具体的な計画があって初めて、その備えは真価を発揮します。
私たちNPO法人ペット防災ネットワークでは、こうした具体的な計画の立て方や、より詳細なノウハウをお伝えするためのセミナーを定期的に開催しています。専門家のアドバイスを直接聞き、他の飼い主さんと情報交換をすることで、あなたのペット防災計画はさらに強固なものになるはずです。
災害は待ってくれません。しかし、私たちには備える時間があります。この記事を読んだ今日が、あなたと愛するペットの未来を守るための、最高のスタート地点です。さあ、今すぐ行動を始めましょう。
正しいペット防災の知識を得るセミナーはこちら https://petbousai.jp/seminar